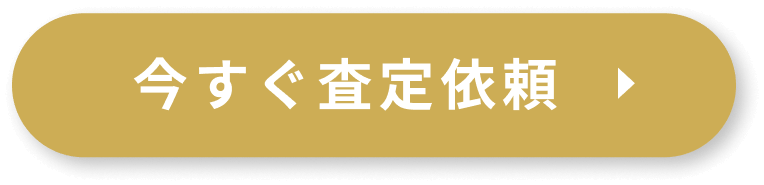不動産を売却すると、税金が上がるのだけではなく、健康保険料も上がるの?と気になっている人もいるのではないでしょうか。
この記事では、不動産売却後に健康保険料が上がるケースと、その仕組みと対策についてご紹介してきます。是非、参考にしてください。
CONTENTS
この記事の目次
不動産売却と健康保険料の関係

まず始めに抑えておくべきは、不動産を売却すると、その売却益が「譲渡所得」として所得に加算されるため、翌年の健康保険料が上がる可能性があるということ。特に国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方、また社会保険の扶養家族の方は注意が必要です。
一方で、会社員や公務員などの社会保険加入者は、不動産売却による利益が健康保険料に影響しません。これは、社会保険の保険料が給与やボーナスを基準に計算されるためです。
不動産を売却する際は、健康保険料への影響を事前に確認し、特別控除の利用や計算方法の工夫で負担を抑えることも可能ですので、その点を覚えておきましょう。
日本の健康保険制度について
日本では国民皆保険制度を採用し、すべての国民が何らかの健康保険に加入しています。健康保険の種類は以下になります。
・社会保険(会社員・パート)
・共済保険(公務員)
・国民健康保険(自営業・年金受給者)
・後期高齢者医療保険(75歳以上)
上記の4つに分かれています。誰しもが健康保険に入っているという前提を押さえておきましょう。
不動産売却後に健康保険料が上がるケース

不動産売却の利益によって 翌年の健康保険料 が増えることがあります。具体的なケースについてご紹介していきますので、是非参考にしてください。
国民健康保険の被保険者
自営業者や年金生活者など、国民健康保険に加入している方が不動産を売却した場合、譲渡所得の発生により翌年度の保険料が増加する可能性があります。
国民健康保険料は前年の所得を基準に算出されるため、不動産売却によって所得が増えると、その分保険料も上がる仕組みになっています。例えば、1,000万円の譲渡所得が発生した場合、保険料の負担が大幅に増える可能性があります。
特に、高額の譲渡所得がある場合は、想定以上に保険料が上がることがあるため、不動産の売却を検討する際は事前に税理士や市区町村の担当窓口に相談すると安心です。
後期高齢者医療制度の加入者
後期高齢者医療制度の加入者も、不動産を売却したことで譲渡所得が発生すると、翌年度の保険料が上がる可能性があります。
75歳以上の高齢者(または65歳以上で一定の障害がある方)が加入する後期高齢者医療制度では、保険料が前年の所得をもとに計算されるため、売却益によって所得が増えた場合、保険料の負担も増加することがあります。
ただし、不動産を売却したからといって必ずしも保険料が上がるとは限りません。特例措置や控除が適用される場合もあるため、事前に自治体の窓口で確認することをおすすめします。
健康保険・共済制度の被扶養者
会社員や公務員の健康保険(協会けんぽや組合健保)または共済制度の扶養に入っている方が不動産を売却した場合、譲渡所得の金額によっては扶養から外れる可能性があります。
健康保険の扶養認定には所得制限があり、一般的に年間130万円(60歳以上や障害者は180万円)を超えると、扶養を外れ、国民健康保険へ加入しなければなりません。その結果、新たに国民健康保険料の負担が発生することになります。
ただし、一時的な収入と判断される場合は、扶養認定に影響しないこともあります。具体的な扱いについては、加入している保険組合や社会保険労務士に相談することをおすすめします。
健康保険料が上がらないケース

社会保険や共済保険に加入している場合、健康保険料は給与やボーナスを基準に算出されるため、不動産売却による譲渡所得が発生しても保険料には影響しません。
たとえば、会社員や公務員が不動産を売却して譲渡所得を得た場合でも、健康保険の保険料は給与や賞与に基づいて決定されるため、売却益が直接反映されることはありません。ただし、扶養に入っている家族が不動産売却によって所得制限を超えた場合は、扶養から外れる可能性があるため注意が必要です。
詳細な条件については、加入している健康保険組合や共済組合に一度確認しましょう。
健康保険料の計算方法と具体例について

ここからは、もう少し健康保険の仕組みについて詳しく知りたいという方向けに、健康保険料の仕組みや具体的な計算の例についてご紹介していきます。
健康保険料の仕組み
保険料の計算方式(所得割・均等割・平等割・資産割の違い)
健康保険料の計算方式には、「所得割」「均等割」「平等割」「資産割」があります。
・所得割:前年の所得に応じて決まる(所得が増えると保険料も増加)。
・均等割:加入者数に応じて一人あたり一定額が課される。
・平等割:世帯ごとに一律で発生する固定額。
・資産割:固定資産の評価額に基づいて計算される(導入自治体のみ)。
不動産売却により譲渡所得が発生すると、所得割が上がる可能性があります。一方、資産割を採用している自治体では、売却後に負担が軽減されることもあります。
自治体ごとに異なる計算方法
健康保険料の計算方法は自治体ごとに異なり、「所得割」「均等割」「平等割」「資産割」の適用や割合が違います。
例えば、資産割を導入している自治体では、固定資産の有無が保険料に影響を与えることがあります。不動産売却後の負担がどう変わるかは、お住まいの自治体のルールを確認することが大切になってきますので、その点を覚えておきましょう。
具体的な計算例(東京都台東区の場合)
年収400万円の健康保険料計算
所得控除後の金額に保険料率を掛け算して健康保険料が決まります。一般的に年収400万円の場合、年間保険料は約33万円程度となります。
不動産売却益300万円が加わった場合
不動産の売却益300万円が加わると、課税所得が増え、それに応じて健康保険料も増加します。譲渡所得が加算されることで、保険料がどのくらい増えるかは、自治体の設定した保険料率によって異なります。
保険料の増加シミュレーション
年収400万円の場合の健康保険料は年間約33万円。これに300万円の不動産売却益が加わると、年間保険料は約42万円程度に増加する可能性があります。増加額の詳細は各自治体の保険料率を元に計算されます。
知っておくべき!健康保険料を抑える方法

ここからは、健康保険料を抑えるための方法について触れていきます。具体的な事例について触れていきますので、是非参考にしてください。
譲渡所得を正しく計算する
不動産売却時に譲渡所得を正しく計算することで、課税対象となる所得を抑えることができます。売却費用(仲介手数料や登記費用)や取得費用(購入時の費用など)をきちんと計上することで、譲渡所得が減少し、結果的に保険料の負担も軽減されます。
もし取得費が不明な場合は、売却価格の5%を概算取得費として計上する方法もあります。必要性に応じて、税理士に依頼するのがおすすめです!
3,000万円特別控除を活用する
居住用不動産を売却した場合、条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。これにより、課税対象となる譲渡所得が大幅に減少し、保険料の負担も軽くなります。
ただし、適用には一定の要件があり、居住していた期間や売却条件が影響するため、事前に確認が必要です。相続した空き家の場合も、特定の要件を満たすと3,000万円控除が適用される場合があるため、売却前に確認しておきましょう。
健康保険組合に事前確認する
不動産売却による一時的な収入がある場合、その収入が健康保険料にどのように影響するかは、事前に健康保険組合で確認することが重要です。譲渡所得がある場合、扶養家族が扶養から外れる可能性があるため、予めそのリスクをチェックしておくことをおすすめします。
また、場合によっては、一時的な収入としてみなされ、保険料の計算方法が異なることもありますので、具体的な取り扱いについても確認しておくようにしましょう。
(まとめ)不動産売却と健康保険料の関係
不動産を売却すると、その売却益(譲渡所得)が翌年の健康保険料に影響を与えることがあります。特に国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している場合、売却益が所得に加算されて保険料が増える可能性があります。一方、社会保険に加入している場合は、売却益は保険料に影響しません。ただし、扶養家族の場合は所得制限を超えると扶養から外れ、保険料が変わることもあります。
対策としては以下になります。
・譲渡所得を正確に計算し、売却費用や取得費用をきちんと計上する。
・3,000万円特別控除を活用する。
・健康保険組合に事前に確認し、扶養から外れるリスクを避ける。
もし不動産売却にお困りの場合は、私たちハウスセイラーズまでご相談くださいませ。