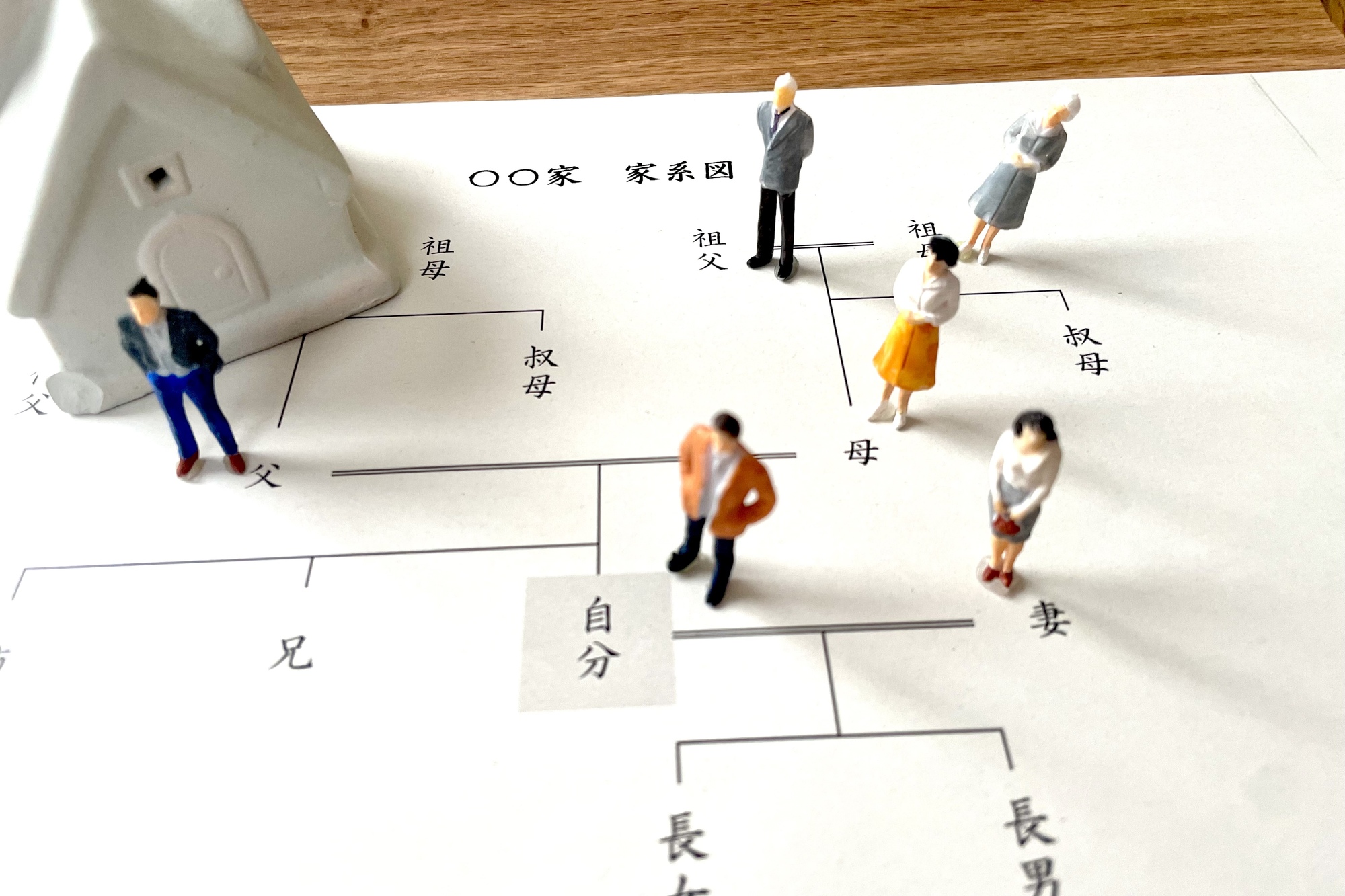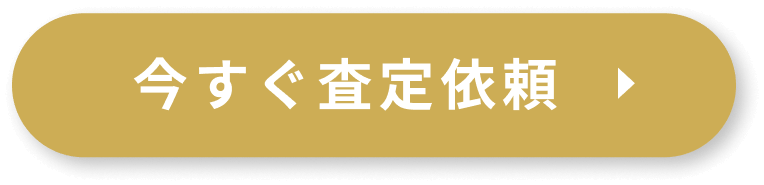不動産の相続は「財産を受け継ぐ」という喜ばしい側面がある一方で、実際には相続人同士の意見調整や複雑な手続きに頭を悩ませるケースが少なくありません。特に相続人が3人いる場合、「誰が不動産を引き継ぐのか」「売却する場合の価格や分配方法をどうするのか」といった問題が重なり、話し合いが停滞してしまうこともあります。
相続登記や税金の申告など、専門知識が求められる手続きも多いため、自己判断だけで進めるのはリスクが高いと言えるでしょう。
本コラムでは、3人での相続が不動産売却を難しくする理由や、トラブルを避けるために頼るべき専門家、そして安心して売却を実現するためのポイントについて解説していきます。
CONTENTS
この記事の目次
- 1. 3人での相続が不動産売却を難しくする理由
- 1-1. 不動産は「共有名義」になるため全員の同意が必要
- 1-2. 売却価格や売却時期の意見が分かれる
- 1-3. 売却益の分配をめぐるトラブル
- 1-4. 手続きの煩雑さと時間的ロス
- 1-5. 感情的な対立が長期化するリスク
- 1-6. 合意形成には「客観的データ」が不可欠
- 2. 不動産売却に必要な基本的な手続きの流れ
- 2-1. ステップ1 相続登記で所有者を確定する
- 2-2. ステップ2 相続人全員の合意を得る
- 2-3. ステップ3 不動産会社に媒介契約を依頼する
- 2-4. ステップ4 売却活動と買主探し
- 2-5. ステップ5 売買契約と決済・引渡し
- 2-6. ステップ6 売却後の税務手続きも忘れずに
- 3. 3人の相続人間で合意を形成するためのポイント
- 3-1. 公平感を保つことが第一歩
- 3-2. 感情論ではなく客観的なデータで判断する
- 3-3. 第三者の専門家を交える
- 3-4. 情報共有を徹底する
- 3-5. 合意の内容を文書化する
- 4. トラブルを回避するために相談すべき専門家
- 4-1. 弁護士 ― 相続人間の対立を法的に解決する専門家
- 4-2. 司法書士 ― 名義変更や登記の専門家
- 4-3. 税理士 ― 複雑な相続税・譲渡所得税を見据えたサポート
- 4-4. 不動産会社 ― 実際の売却戦略を担うパートナー
- 4-5. 専門家の連携が成功の鍵
3人での相続が不動産売却を難しくする理由

相続財産に不動産が含まれる場合、その処分は他の財産と比べて複雑になりがちです。特に相続人が3人いるケースでは、売却に向けた話し合いがスムーズに進まないことが多く、時間や労力がかかる傾向があります。
ここでは、3人での相続が不動産売却を難しくする主な理由を整理してみましょう。
不動産は「共有名義」になるため全員の同意が必要
相続登記が完了すると、相続不動産は通常「相続人全員の共有名義」となります。この場合、不動産を売却するためには、 3人全員の同意が必須です。つまり、2人が賛成しても1人が反対すれば取引は成立しません。
不動産の売却は、全員一致が求められる点が大きな特徴です。人数が増えるほど意見の不一致が起こりやすく、特に「3人」というバランスは2対1に分かれやすく、合意形成を難しくする要因となります。
売却価格や売却時期の意見が分かれる
3人の相続人は、それぞれ異なる生活環境や経済状況を抱えています。そのため、売却に対する考え方も大きく異なります。
「早く現金化して生活資金に充てたい」
「できるだけ高く売却するために相場を見ながら時間をかけたい」
「思い出が詰まった家なので手放したくない」
こうした意見が出れば、話し合いは平行線になりやすく、結論が先延ばしになります。
特に3人の場合、2人が賛成しても1人の強い反対によって売却が進められない状況が生まれがちです。
売却益の分配をめぐるトラブル
不動産を売却すれば、その代金を3人で分けることになりますが、この「分配」をめぐってトラブルになるケースも少なくありません。
例えば、固定資産税や修繕費を長年支払ってきた人が「自分の取り分を多くすべきだ」と主張する場合があります。また、「生前に親から兄に多く相続させると聞いていた」など、曖昧な記憶や口約束が議論に持ち込まれることもあります。
法律的には法定相続分や遺言によって配分が決まりますが、感情面で納得できない人が出ると、家族間での対立が深刻化する可能性があります。3人という人数は「多数派と少数派」が分かれやすく、分配トラブルを一層大きくしがちです。
手続きの煩雑さと時間的ロス
不動産を売却する際には、売買契約書や重要事項説明書などに 全員が署名・押印する必要があります。3人のうち1人でも遠方や海外に住んでいる場合、書類のやり取りに時間がかかり、売却活動が遅れることもあります。
また、 契約や決済の場に3人全員が立ち会う必要があるケースもあり、スケジュール調整だけで数週間から数か月かかることもあります。人数が多いほど、この「調整コスト」が大きくなり、スムーズな売却を妨げる要因になります。
感情的な対立が長期化するリスク
不動産には、単なる資産としての価値だけでなく、家族の思い出や歴史が詰まっています。そのため「売却したくない」「できれば残したい」といった感情が強く働くケースも多いです。
3人の場合、「兄と妹は売却を望むが、弟は強く反対」といった構図になりやすく、家族関係に亀裂が入る恐れもあります。相続は法律と感情の両面を調整する必要があるため、単純な金銭問題では片付けられないのが難しい点です。
合意形成には「客観的データ」が不可欠
以上のように、3人の相続人がいると不動産売却は容易ではありません。しかし解決策がないわけではなく、共通の判断材料を持つことが有効です。
当社が活用する独自のデータベースや「売出後半年以内の売却成功率90%」「売出価格と成約価格の乖離率5.3%」といった実績は、相続人全員が納得感を持つための有効な材料になります。
公平で透明性の高い基準を提示することで、3人の間に生まれる意見の隔たりを縮め、合意形成を後押しできるのです。
不動産売却に必要な基本的な手続きの流れ

相続人が3人いる場合、不動産を売却するためには、通常の売却と比べて慎重かつ正確な手続きが求められます。特に相続登記の義務化(2024年4月施行)により、名義の整理を避けて売却を進めることはできなくなりました。
ここでは、不動産売却に必要な基本的な流れを順を追って解説します。
ステップ1 相続登記で所有者を確定する
まず最初に行うべきは、 相続登記による名義変更です。被相続人(亡くなった方)の名義のままでは売却できません。2024年からは相続登記が義務化され、3年以内に手続きを行わないと過料(罰則金)が科される可能性もあるため、早めの対応が必要です。
相続登記では、遺言の有無や遺産分割協議の結果に基づき、3人全員が共有名義人として登記されるケースが一般的です。この段階で「誰がどの割合を持つのか」が確定するため、後々の売却益の分配にも直結します。司法書士に依頼して正確に進めるのが安心です。
ステップ2 相続人全員の合意を得る
次に重要なのが、 売却に向けて3人全員の合意を形成することです。共有名義の場合、1人でも反対すれば売却は進められません。
この段階でトラブルになりやすいのが、売却価格や売却時期に対する考え方の違いです。そのため、まずは不動産会社に査定を依頼し、客観的な市場価格をベースに話し合うことが欠かせません。
当社では足立区・北区エリアに特化した独自データを活用し、実際の取引事例を示すことで、相続人同士が冷静に判断できる材料をご提供しています。
ステップ3 不動産会社に媒介契約を依頼する
相続人全員の合意が得られたら、不動産会社と媒介契約を締結します。媒介契約には「専任媒介」「一般媒介」などの種類がありますが、相続人3人が関わる場合は、 売却活動の透明性を保てる体制が求められます。
当社では、売却活動の進捗や反響状況をこまめに共有し、全員が同じ情報を確認できるようにサポートします。
こうすることで「知らない間に勝手に決められた」という不満を防ぎ、公平感のある売却を実現できます。
ステップ4 売却活動と買主探し
媒介契約を結んだら、実際に売却活動をスタートします。広告や内覧対応を通じて買主を探すプロセスです。
足立区・北区を中心とした当社の販売実績では、売出から半年以内に約90%の物件が成約しています。
このスピード感を実現できるのは、地域に根ざした独自のネットワークとデータベースがあるからです。複数の買主候補を比較検討できるため、相続人全員が納得できる条件で売却しやすくなります。
ステップ5 売買契約と決済・引渡し
買主が決まったら、売買契約を締結します。この 契約には相続人3人全員の署名・押印が必要です。書類のやり取りや立会いの日程調整は煩雑ですが、不動産会社がスケジュール管理を担うことでスムーズに進められます。
決済・引渡し時には、残代金の受け取りや固定資産税の清算、登記手続きが行われます。売却代金は原則として相続分に応じて分配されますが、トラブル防止のために司法書士や税理士のサポートを受けることをおすすめします。
ステップ6 売却後の税務手続きも忘れずに
不動産を売却した場合、譲渡所得税の申告が必要となります。相続人が3人いる場合、それぞれの持分に応じた利益に課税される仕組みです。特例(3,000万円特別控除など)が利用できるケースもあるため、税理士に確認して適切に申告を行いましょう。
3人の相続人間で合意を形成するためのポイント

相続人が3人いる場合、不動産の売却を進めるには「全員一致」が大前提となります。しかし、それぞれの生活環境や考え方が異なる中で、意見をまとめるのは簡単ではありません。スムーズに売却を進めるには、合意形成のための工夫が不可欠です。
ここでは、3人の相続人が納得感を持って話し合いを進めるための具体的なポイントを解説します。
公平感を保つことが第一歩
3人の間で意見が対立しやすいのは、「公平かどうか」という感覚の違いです。売却益の分配にしても、単純に3等分するのが妥当と考える人もいれば、税金や管理費を負担してきた人の取り分を増やすべきだと主張する人もいます。
このとき大切なのは、誰かの主張だけを優先するのではなく、 「法律上のルール」と「話し合いによる調整」の両方を踏まえることです。法定相続分に基づく分配をベースにしながら、追加負担をしてきた相続人に感謝を込めて一定額を上乗せするなど、全員が納得できる形を模索することが合意形成の第一歩となります。
感情論ではなく客観的なデータで判断する
「売りたい」「売りたくない」「もっと高く売れるはずだ」など、相続不動産をめぐる議論は感情的になりがちです。こうした状況を避けるためには、客観的なデータをもとに話し合うことが欠かせません。
当社のように足立区・北区の直近の成約事例や相場データ、売出価格と成約価格の乖離率(当社の平均5.3%)といった数字を提示すれば、感覚や思い込みではなく「現実的にどれくらいで売れるのか」を全員が共通認識として持つことができます。事実に基づいた会話ができれば、感情的な対立を抑え、冷静に判断できる環境が整います。
第三者の専門家を交える
相続人3人だけで話し合おうとすると、どうしても家族間の感情が前面に出てしまい、議論が平行線をたどりやすくなります。そこで有効なのが、不動産会社や司法書士、税理士といった第三者の専門家を交えることです。
不動産会社は市場価格や売却戦略の専門家として、透明性のあるデータを提供し、公平な視点からアドバイスを行います。司法書士は登記や権利関係を整理し、税理士は売却後の税務面をサポートします。第三者の意見を取り入れることで、「誰かの言い分」ではなく 「専門家が示す客観的な意見」として受け入れやすくなり、合意形成が進みやすくなります。
情報共有を徹底する
合意形成において意外と多いのが、「自分だけ知らされていない」という不満です。特に3人いると、2人だけで先に打ち合わせを進めてしまい、残る1人が不信感を抱くケースもあります。こうした不公平感は、大きな対立へと発展しかねません。
当社では売却活動の進捗や査定結果、内覧の反応などを全員に共有し、誰も情報から取り残されない体制を整えています。全員が同じ情報を見ている状態で話し合うことが、信頼関係を保ち、スムーズな合意形成につながります。
合意の内容を文書化する
話し合いで合意に至った内容は、 必ず書面に残しておくことが大切です。口約束のままでは後になって「そんなことは言っていない」とトラブルになる恐れがあります。
「売却価格は◯◯万円を下限とする」「売却益は法定相続分で分ける」など、合意した条件を簡単な合意書にまとめるだけでも安心感が生まれます。司法書士や不動産会社の立ち会いのもとで文書化すれば、さらに信頼性が高まります。
相続人が3人いる場合の不動産売却は、意見の違いが出やすく、調整に時間がかかることが少なくありません。しかし、合意形成をスムーズに進めるには「公平感の確保」「客観的データの活用」「第三者の専門家の関与」「情報共有の徹底」「合意内容の文書化」といった工夫が効果的です。
トラブルを回避するために相談すべき専門家

不動産の相続は「財産を受け継ぐ」というイメージが強いですが、実際には相続人同士の意見の対立や複雑な法律・税務の問題が絡み合い、スムーズに進まないことが少なくありません。相続人が3人以上いる場合には、売却に必要な合意形成や登記、税金対策など、多方面の知識が求められます。そのため、自己判断で進めるのではなく、専門家に相談することがトラブル回避の近道となります。
ここでは、不動産売却を伴う相続において頼るべき専門家について整理していきます。
弁護士 ― 相続人間の対立を法的に解決する専門家
相続人が複数いる場合、最大のリスクは「意見の食い違い」です。売却価格への不満、分配方法の認識違い、さらには過去の家族関係に起因する感情的な対立まで、話し合いだけでは解決できないケースも多々あります。こうしたときに力を発揮するのが弁護士です。
弁護士は法律に基づき、公平な解決策を提示してくれるだけでなく、必要に応じて調停や訴訟に発展した場合の代理人としても対応してくれます。例えば、相続人の1人が「売却ではなく自分が住み続けたい」と主張した場合、法律上の権利関係や共有物分割請求といった手続きを進める必要があり、専門的な判断が求められます。
こうした局面で弁護士が介入することで、相続人同士の直接対立を避け、冷静に前進することが可能になります。
司法書士 ― 名義変更や登記の専門家
不動産売却をするためには、まず名義を相続人に移す「相続登記」が必要です。相続人が3人いる場合、誰の名義にするのか、あるいは共有名義にするのかを決めなくてはなりません。これを正しく行わなければ、売却の手続き自体が進められなくなります。
司法書士は、こうした登記の専門家です。相続関係を証明するための戸籍収集や遺産分割協議書の内容確認など、法律上の要件を満たす手続きを担います。例えば「共有名義にした場合の将来的なリスク」や「代表者を決めて単独名義にしたほうが良いケース」など、実務に基づいた具体的なアドバイスをしてくれる点も心強いです。
相続登記は2024年4月から義務化されており、放置すると過料が科される可能性もあるため、早めに司法書士へ相談するのが安心です。
税理士 ― 複雑な相続税・譲渡所得税を見据えたサポート
不動産を相続した場合、一定の基礎控除を超えると相続税が発生します。また売却した際には譲渡所得税もかかるため、「相続+売却」という二重の税務リスクを考慮しなければなりません。相続人が3人いると分配方法によって課税額が変わるケースもあり、税務上の最適解を導き出すのは容易ではありません。
税理士に相談することで、節税につながる具体的な方法を提案してもらえます。例えば「小規模宅地等の特例を使えるか」「売却時期を調整すべきか」「不動産を現金化してから分割する方が有利か」といった判断は、専門的な知識がなければ誤った選択につながりかねません。税務はトラブルが表面化しにくい分、後から追徴課税という形で大きな負担になる可能性があるため、早期の相談が重要です。
不動産会社 ― 実際の売却戦略を担うパートナー
最終的に不動産を売却する場面では、不動産会社のサポートが不可欠です。相続人が3人いる場合、それぞれが納得できる売却価格や売却方法を提示できるかがポイントとなります。
特に地域に精通した不動産会社であれば、地元の相場や買い手の傾向を踏まえた適切な価格設定が可能です。また、不動産会社は売却活動の窓口として、複数の相続人とのやり取りを代行する役割も果たします。情報共有の齟齬や感情的な衝突を最小限に抑える効果があるため、 信頼できるパートナー選びが重要になります。
専門家の連携が成功の鍵
相続に関わる課題は、法律・登記・税務・売却と領域が分かれています。しかし実際にはこれらが密接に関わり合うため、1人の専門家だけに依頼するのではなく、 複数の専門家が連携してサポートする体制が理想です。「司法書士が相続登記を行い、税理士が税務上の影響を確認し、不動産会社が市場に合わせて売却を進める」といった流れがあれば、無駄なく安全に手続きが進みます。
専門家と連携して安心の相続不動産売却を実現
相続人が3人いる不動産売却は、合意形成の難しさや複雑な法律・税務の問題が絡み合い、想像以上に手間やリスクを伴います。トラブルを避けるためには、弁護士・司法書士・税理士といった専門家に早い段階から相談し、それぞれの分野で正しい判断を導くことが重要です。そして、実際の売却を担う不動産会社は、価格設定や販売戦略だけでなく、相続人間の調整役としても大きな役割を果たします。
地域に根ざし、多くの実績と専門家ネットワークを持つ当社であれば、複雑な相続売却でも安心して進めていただけます。
複数の専門家と連携しながら、納得と安心の不動産売却を実現することこそが、相続トラブル回避への最良の道です。