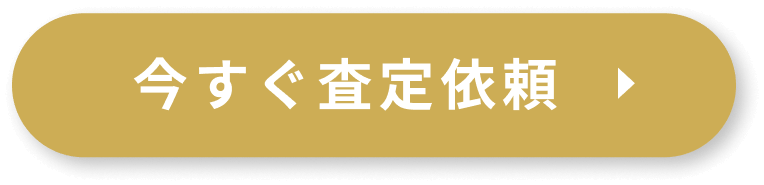リースバックとは、不動産を売却したもとの所有者が、買主からその不動産を借りて引き続き利用する仕組みのことを指します。この記事では、不動産オーナー向けにリースバックの仕組み・活用法・メリット・注意点を徹底解説。資金調達や相続対策としての活用まで紹介します。
CONTENTS
この記事の目次
- 1. リースバックとは?不動産オーナーが知っておくべき基本知識
- 1-1. 売却と賃貸のハイブリッド?オーナーの視点で解説
- 1-2. 住宅用と事業用リースバックの違い
- 2. なぜ今、不動産オーナーがリースバックに注目しているのか?
- 2-1. 資金調達の新しい選択肢
- 2-2. バランスシートの軽量化と節税対策
- 2-3. 事業の継続性確保・相続対策としての有効性
- 3. リースバックの具体的な仕組みと流れ
- 3-1. 売却からリース契約までのステップ
- 3-2. 賃料の決まり方と期間の目安
- 3-3. 買戻しオプションがある場合の注意点
- 4. メリットとデメリットを徹底比較
- 4-1. 資金化しながら物件を使い続けられるメリット
- 4-2. 賃料負担・将来の明渡しリスクなどデメリット
- 4-3. メリットが活きるケース/デメリットが重くなるケース
- 5. 他の手法との違いと使い分け方
- 5-1. リースバックと通常の売却の違い
- 5-2. リバースモーゲージとの違い
- 5-3. 不動産担保ローンや任意売却との比較
- 6. 不動産オーナーがリースバックを活用すべきタイミングとシチュエーション
- 6-1. キャッシュが必要な時の資金調達手段として
- 6-2. 後継者不在時の事業整理や資産移行
- 6-3. 収益物件の組み替え・再投資戦略
- 7. 注意点と信頼できる業者の選び方
- 7-1. 契約内容で確認すべきポイント
- 7-2. 悪質業者を避けるチェックリスト
- 7-3. 税務・法律の専門家への相談も重要です
- 8. リースバックは「資産活用」の戦略になる
リースバックとは?不動産オーナーが知っておくべき基本知識

リースバックとは、不動産を第三者に売却し、その後同じ物件を賃貸として借り直す仕組みのことです。オーナーにとっては、保有資産を現金化しつつ、引き続き同じ物件を使用できる点が特徴です。
近年、特に注目されているのが「自宅リースバック」と呼ばれる形態。これは、自宅をリースバック専門の事業者などに売却した後、そのまま賃貸契約を結び、元の住まいに住み続けるというものです。
この方法を活用すれば、不動産を現金化しながらも住み慣れた自宅から引っ越す必要がないので、近年注目されています。
売却と賃貸のハイブリッド?オーナーの視点で解説
リースバックでは、不動産の所有者は売却と同時に賃貸借契約を締結し、「所有者」から「賃借人」へと変わります。これは、いわば「売却と賃貸を組み合わせたハイブリッド型の資産活用」です。
オーナーにとっての最大のポイントは、資産を手放すことで資金を確保しながらも、生活や事業の拠点を変える必要がないという柔軟さにあります。
たとえば、住宅ローンの返済に困っていたり、老後の生活費を準備したいと考えていたりする場合でも、住み慣れた家を手放さずに済むという安心感もあります。
住宅用と事業用リースバックの違い
リースバックには大きく分けて「住宅用」と「事業用」があり、それぞれ対象者や目的が異なります。どちらも「不動産を売却しつつ、引き続き利用する」という点では共通していますが、その背景や活用の意図は大きく異なります。
まず、住宅用リースバックは、主に個人、特に高齢者や住宅ローンの返済に悩んでいる方が対象となります。例えば、「老後資金を確保したいけれど、住み慣れた自宅は手放したくない」といったニーズに応える形で利用されるケースが多くあります。
また、病気や介護などでまとまった資金が必要になった場合にも有効です。住宅用リースバックは、生活の継続と安心感を重視する人にとって、資産を流動化しながら住まいを維持できる手段として注目されています。
一方、事業用リースバックは、企業や個人事業主が保有するオフィスビル・工場・店舗などの事業用不動産を対象としたものです。こちらは主に資金調達や財務戦略の一環として活用されます。
なぜ今、不動産オーナーがリースバックに注目しているのか?

ここまでリースバックについて触れてきましたが、ここからは、さらにリースバックが何故不動産オーナーに注目されているのか、という部分について具体的に触れていきます。
資金調達の新しい選択肢
リースバックは、金融機関からの融資に依存せずにまとまった資金を確保できるという側面から、資金調達手段として注目されています。通常、事業拡大や運転資金の確保には銀行からの借入や不動産担保ローンなどを検討することが一般的ですが、こうした方法には審査のハードルや借入限度額、返済義務といった制約が伴います。
一方、リースバックを活用すれば、保有する不動産を売却して現金化することで、資産を有効活用しながらも、その不動産を引き続き事業や生活の拠点として利用することが可能です。売却によって得た資金は、設備投資、資金繰りの改善、新規事業への投資など、さまざまな目的に活用できます。
さらに、借入をせずに資金を得られるということは、金融機関との与信枠を温存できるという点でも大きなメリットです。今後の戦略的な資金調達や、突発的な支出に備える上でも、リースバックは有効な選択肢といえます。
バランスシートの軽量化と節税対策
リースバックは、企業にとって非常に有効な財務戦略となり得ます。特に、資産のオフバランス化が可能になる点が大きな利点です。通常、企業が保有する不動産は、バランスシートにおいて資産として計上され、減価償却費などの負担が発生します。
しかし、リースバックを活用することで、不動産を売却し、その後賃貸契約を結ぶことで所有権は移転しますが、引き続き利用することができます。この結果、オフバランス化が実現し、バランスシート上での資産負担を軽減することができます。
オフバランス化が進むことで、財務指標の改善が期待できます。資産規模を縮小することにより、自己資本比率の向上や、他の財務指標の改善が可能となり、企業の財務体質が強化されます。また、特に多額の不動産を所有している企業にとっては、財務状況の健全化に繋がり、経営上の自由度が広がります。
さらに、法人にとって見逃せないポイントは、リースバックによって支払う賃貸料が損金扱いとなることです。リース契約に基づく賃料支払いは、税法上、経費として処理することが可能です。これにより、法人税の負担を軽減できるため、節税対策として非常に有効です。特に、事業規模が大きい企業や、不動産を保有している企業にとっては、この節税効果は大きなメリットとなります。
このように、リースバックを活用することで、バランスシートの軽量化や財務指標の改善、さらに節税対策を同時に進めることができ、企業の経営戦略において重要な役割を果たします。
事業の継続性確保・相続対策としての有効性
経営者の高齢化が進む中、後継者問題や事業継承が大きな課題となっています。リースバックは、資産を売却し現金化しながらも、引き続き事業を継続できる仕組みです。特に後継者が決まっていない場合、事業整理や資産の流動化を進めつつ、事業の運営を続けることが可能です。
また、リースバックは相続対策としても非常に有効です。不動産を売却して現金化することで、相続時に不動産評価額を低減させ、相続税の負担を軽減できます。
さらに、資産のオフバランス化が進むため、相続財産を整理しやすくなります。このように、事業の継続性を確保しつつ、相続時の負担軽減にもつながるため、経営者にとって重要な選択肢となります。
リースバックの具体的な仕組みと流れ

売却からリース契約までのステップ
以下のステップで、売却からリース契約までを行われます。
1、物件査定
2、売却契約の締結
3、所有権移転
4、リース契約締結
5、月々の賃料支払い
賃料の決まり方と期間の目安
リースバックにおける賃料は、一般的にその物件の市場賃料や売却額を基準に算出されます。多くの場合、売却価格に対する利回り(例えば5〜8%程度)をもとに月額賃料が設定されることが多く、立地や物件の状態、需要状況によって上下することもあります。売却価格を高く設定した場合、賃料も比例して高くなる傾向があるため、資金調達額とその後の負担バランスをよく検討する必要があります。
契約期間については、2〜5年程度が一般的な目安です。ただし、期間満了後の再契約の可否や、契約更新時の条件変更(賃料の見直しなど)についても事前に確認しておくことが重要です。
特に長期的にその物件を使い続けたい場合は、更新の柔軟性や買主(リースバック事業者)の方針をしっかり把握しておくことが、トラブル回避につながります。
買戻しオプションがある場合の注意点
リースバック契約において、将来的に物件を買い戻すことを検討している場合は、「買戻しオプション」を事前に契約に盛り込むことが重要です。
買戻しの意思があるにもかかわらず、条件が曖昧なまま契約してしまうと、後から想定外の価格を提示されたり、買戻し自体を拒否されたりするリスクがあります。
買戻し条件には、具体的な価格や買戻し可能な期間、手続きの流れ、違約時のペナルティなどを明記しておくことが理想的です。また、契約書の文言があいまいだと、トラブルに発展する可能性もあるため、契約前に専門家の確認を受けることをおすすめします。
さらに、リースバック事業者によっては買戻しオプションに対応していない場合もあるため、業者選びの段階で対応可否を確認しておくことも大切です。物件を手放した後の選択肢を広げておくためにも、買戻しの計画があるなら最初から明確な取り決めを行っておくことが、安心してリースバックを活用するためのカギとなります。
メリットとデメリットを徹底比較

資金化しながら物件を使い続けられるメリット
・資産の流動化
・借入せずに資金調達
・事業・生活拠点を維持可能
賃料負担・将来の明渡しリスクなどデメリット
・賃料が市場価格より割高になることも
・契約更新ができない可能性
・長期的にはコストが高くなる
メリットが活きるケース/デメリットが重くなるケース
リースバックは状況に応じて非常に有効な手段となり得ますが、すべてのケースにおいて最適とは限りません。メリットが最大限に活きるのは、短期間でまとまった資金が必要なときや、将来的に物件の買戻しを予定している場合です。
たとえば、急な資金ニーズに対応したいが、生活や事業の拠点を変えたくないという方にとっては、現金化と使用継続を両立できる点で非常に有効です。また、相続や事業承継の計画の一環として一時的に手放し、タイミングを見て買い戻すようなケースでも柔軟に活用できます。
一方で、リースバックのデメリットが重くなるのは、収益性の低い物件や、長期的にその不動産を使い続けることを前提としている場合です。というのも、リース契約に基づく賃料は、長期にわたって支払いが発生するため、トータルコストが割高になる可能性があります。さらに、契約更新が保証されていない場合、数年後に退去を求められるリスクもあるため、安定した利用を最優先する方には不向きなケースもあります。
そのため、リースバックを検討する際は、自身の資金計画や将来の事業・生活設計に照らし合わせたうえで、メリットとデメリットをしっかり比較することが重要です。
他の手法との違いと使い分け方

リースバックと通常の売却の違い
通常の不動産売却では、物件の所有権と共に使用権も完全に手放すことになります。つまり、売却後はその物件に住み続けたり、事業で使用したりすることはできません。
一方、リースバックは売却と同時に賃貸契約を締結することで、物件の使用を継続することができます。これにより、資産の現金化と居住・利用の維持を両立できるという点が大きな違いです。
生活基盤や事業拠点を変えずに資金調達したい場合に有効な手段といえます。
リバースモーゲージとの違い
リバースモーゲージは主に高齢者向けに提供される金融商品で、自宅を担保に金融機関から融資を受ける仕組みのことを指します。毎月の返済は不要で、借入残高は死亡時や退去時に物件売却で清算されるのが一般的です。
一方、リースバックは「融資」ではなく「売却」によって資金を得る手法であり、借金が残らないという点が大きな違いです。
また、リバースモーゲージは金融機関の審査が厳しく、利用できる物件や地域に制限がある場合もあるため、すぐに資金が必要な場合や審査に通るか不安な場合にはリースバックが選ばれることもあります。
不動産担保ローンや任意売却との比較
不動産担保ローンは、保有している物件を担保に金融機関から融資を受ける仕組みであり、当然ながら返済義務が発生します。金利負担や返済計画がネックになる場合もあるため、借入を避けたい場合には適していません。対してリースバックは売却による資金獲得であるため、借金として残るものはありません。
任意売却は、住宅ローンが返済困難になった際に債権者(金融機関など)と合意の上で行う売却方法で、主に債務整理の一環として使われます。
任意売却では売却後に物件に住み続けることはほとんどできないため、住み慣れた自宅を維持したいというニーズには適していません。この点でも、リースバックは「住み続ける」ことを前提とする仕組みとして大きく異なります。
不動産オーナーがリースバックを活用すべきタイミングとシチュエーション

キャッシュが必要な時の資金調達手段として
リースバックは、迅速に資金を確保したいときの柔軟な選択肢となります。特に、金融機関からの借入が難しい、あるいは借入枠をこれ以上圧迫したくない場合などに有効です。
たとえば、一時的な資金ショートの回避や、設備投資・医療費・教育費など急な出費への対応策として活用されることもあります。手続きが比較的スピーディであることから、「今すぐ現金が必要だが、物件を手放したくない」というニーズに応える手段といえるでしょう。
後継者不在時の事業整理や資産移行
中小企業や個人事業主の間では、経営者の高齢化により事業承継の課題が深刻化しています。後継者が不在である場合、事業の整理や廃業の準備として、保有資産を現金化しておくことは合理的な判断です。
リースバックを利用することで、事務所や工場などの物件を手放すことなく、段階的な撤退・縮小が可能になります。また、相続を見据えた資産の分割や換金にも役立ち、トラブルを未然に防ぐ手段としても注目されています。
収益物件の組み替え・再投資戦略
市場環境の変化に伴い、保有している不動産の収益性が低下した場合には、資産の入れ替えを検討することが重要です。リースバックにより、既存の不動産を現金化し、その資金をもとにより収益性の高い物件への再投資を行うことができます。
また、空室リスクや維持コストの高い物件からの転換としても有効で、投資効率を見直したいオーナーにとっては戦略的な判断材料となるでしょう。
特に法人の場合、キャッシュフローの健全化と財務の柔軟性を高める手段としても活用されています。
注意点と信頼できる業者の選び方

契約内容で確認すべきポイント
・賃料水準
・契約期間と更新条件
・買戻しオプションの有無と条件
上記のポイントをしっかりと抑えておきましょう。
悪質業者を避けるチェックリスト
・相場よりも過度に高い賃料を提示する
・契約書に不明瞭な点が多い
・実績が不明・口コミがない
税務・法律の専門家への相談も重要です
契約前には税理士・弁護士・不動産鑑定士など、専門家のアドバイスを求めることが大事になってきます。自分だけで判断して進めてしまうと、大きなトラブルへと発展してしまう可能性がありますので、その点を覚えておきましょう。
リースバックは「資産活用」の戦略になる
リースバックは単なる不動産売却ではなく、資産を活かすための経営的な選択肢です。不動産オーナーにとって、資金調達・事業戦略・相続対策といった多角的な課題に対応できる手段として、今後ますます注目されていくことが予測されます。
ただし、契約内容や業者選定を誤ると大きなリスクにもなり得ます。適切な理解と慎重な判断が、リースバックを成功に導くカギとなりますので、その点を覚えておきましょう。
不動産売却でお困りなら「ハウスセイラーズへ」
不動産売却でお悩みの方は、地域密着型の「ハウスセイラーズ」にご相談ください。足立区・北区を中心に、約90%の物件を半年以内に売却してきた実績があります。豊富な地域データと独自の販売戦略を駆使し、お客様一人ひとりに最適な売却プランをご提案。
相続や税務の専門家とも連携し、初めての方でも安心して任せられるサポート体制を整えています。スピード・価格・信頼を重視した売却なら、ハウスセイラーズにお任せください。